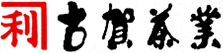八女茶の歴史(江戸時代)
八女茶は江戸時代、どのように生産され飲まれていたのか、歴史を紐解いてみましょう。
江戸時代には、お茶は庶民の間にも広まっていっていきました。「日常茶飯事」という慣用句が出来たのも江戸時代だと言われています。
しかし、元文3年(西暦1738年、江戸時代中期)に永谷宗円らによって、現在の煎茶製法の原型が発明されるまで、一般的に飲まれていたのは、茶葉をヤカンの湯で煮出すことによって成分を抽出する煎じ茶でした。急須が発明されたのも江戸時代後期で、現在の「急須で煎茶を淹れる」という形が一般に広まったのもその辺りからだと思われます。
長い江戸時代を、前期~中期、後期、末期の3つ分けてみていきましょう。
江戸時代前期~中期
江戸時代前期、三代将軍・徳川家光が発令した『慶安御触書』によって茶は贅沢品と戒められ、安定的な生産の為には高価な肥料であった干鰯や油粕のような高窒素肥料を購入しなければならず、それだけの経済的な余裕も農村部には難しいものでした。
しかし結果的に、茶等換金作物の生産地である農村を貨幣経済化させていく要因の一つに繋がっていったと言えます。
当時は現在の茶園や茶畑のような栽培方法ではなく、山の斜面に種子から茶樹を育て、収穫しているだけで安定しておらず、主に久留米藩(現在の福岡県久留米市に藩庁を置いた藩)の中で流通していました。
江戸時代中期になると、少量ではありますが、京都や大坂へ八女から「鶯」、「初花」と称する釜炒り茶が流通し、宝暦明和年間 (1751~1771年) を通じて「鹿子尾茶(八女茶の発祥である鹿子尾村から名付けられたと思われる)」として人気を博しました。
江戸時代後期
江戸時代後期になると、永谷宗円らが開発した現在の日本緑茶の原型となる宇治式青製煎茶製法が伝わります。
天保2年(1831年)に上妻郡山内村(現在の八女市山内)の古賀平助が試製し、大津簡七も宇治から茶師の吉朗兵衛らを雇い試製しました。
江戸時代は江戸、京都、大阪を中心とした市場で構成され、嗜好品はごく一部の層のために作られており、青製煎茶は江戸の山本嘉平に代表される商人たちによって宇治から江戸などへ供給されていました。
八女地域の商業資本の限界もあり、生産量は伸びませんでした。
江戸時代末期
安政3年(1856年)に長崎の出島でお茶の貿易商であった大浦慶が、イギリス人貿易商ウィリアム・オルトとお茶の直接取引を開始し、アメリカへ日本茶(釜炒り茶や日干し茶)が輸出されると、八女のお茶も貿易品として注目されるようになり、文久3年(1863年)長崎港で英国人と直接取引を開始しました。
また、1859年ジャーディンマセソン商会長崎代理店としてトーマス・ブレーク・グラバーが開いたグラバー商会は、当初アヘン戦争で疲弊した清国の貿易代替地として生糸やお茶といったアジア的な商材の輸出を中心に行っていました。
八女福島地区の商家に和紙を買い付けに来た記録が残っており、八女茶も同時に取引されていたと思われます。
安政6年(1859年)江戸幕府が、箱館、新潟、横浜、神戸、長崎を開港すると、日本からアメリカに輸出する緑茶も年々増加傾向をたどり、八女地方でも緑茶(主に日乾製や釜炒製)の製品化を目指した取り組みが行われるようになりました。
それにより八女地方東部の山々にはいたるところに茶樹が見られるようになりました。
しかし、この時期も茶の栽培は近代的な茶園ではなく、茶樹を山に植えているだけの粗放なものであったため、茶葉の生産も栽培というよりむしろ採取の形で行われていました。
製造技術も未熟な焙炉や天日干しを利用した黒製法や釜炒り製法で行われ、特に輸出を急ぐあまり日光乾燥や日陰干しの際に十分乾燥されないまま出荷された黒製茶は、色や香りが悪いため、輸入国のアメリカでは大きな問題となりました。